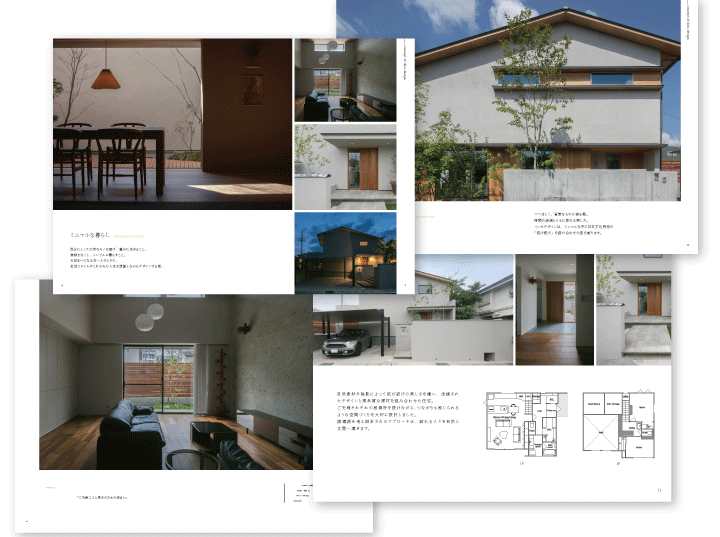片付く家の間取りのコツ|散らからない家を設計する方法

片付けてもすぐ散らかるし、テーブルの上もこまごましたもので、いつも雑然としているとお悩みではありませんか?その原因は「収納量の不足」ではなく、日々の動きに合っていない間取りにあります。
片付く家は、「動線×定位置×浅い収納」でつくるものです。帰宅して玄関で荷物を降ろしてからリビングへ行くまでの動線作りや、テーブル上を空に保つための細々した物の定位置化によって、自然と片付く家になっていきます。
さらに、必要な作業が全て同じエリアで完結できるキッチンやランドリー、子どもが自分で片付けられる高さの工夫など、散らからない家の間取りのコツを、わかりやすく解説します。
目次
片付く家は「動線×定位置×浅い収納」で実現できる!

散らかる原因の9割は、物の量ではなく動線と収納の設計ミスです。片付く家は、動くルート上に「戻す場所」があり、棚や引き出しが浅くて中身が一目でわかるようになっているのです。
まずは、日々の家事や身支度を一筆書きにし、使う場所のすぐそばに定位置を作ります。さらに、奥行きが浅い収納で見える化する。この3点を押さえれば、片付く間取りになります。
歩数と手数を減らす「2分動線ルール」
家事や身支度の一単位を、歩数と手数の合計が2分以内に収まるよう設計します。たとえば帰宅後は、
- 玄関で荷物を降ろす
- 手洗い
- アウターとバッグをしまう
- LDKへ
ここまでを一直線にします。
同じように、
- 配膳と片付けは、食器棚と食洗機の距離を近接させて往復回数を最小化
- 洗濯は洗う→干す(または乾燥)→たたむ→しまう、を同じフロアや隣接空間で完結
動線が短いほど、出しっぱなしの発生源が消えます。
「使う場所のすぐそこ」にしまえる場所を定位置化
物は使う場所の半径2歩以内に定位置をつくります。
- 玄関には鍵・郵便物・通学通勤セットがおける場所
- ダイニング脇には書類と筆記具の一次置き場
- リビング学習には教科書と充電ステーション
家族の誰が見てもわかる、名前付きの仕切りやラベルを用意するとよいでしょう。定位置が近いほど、散らかる前に自然と戻せます。
浅い奥行き・引き出し中心で「見える化」する
片付かない最大の敵は、収納場所が足りないのではなく、収納棚の「見えない奥」なのです。
パントリーやリビング収納は奥行き20〜30cmを基準に、棚は可動式で高さを細かく調整します。引き出しは中身が一目で分かる浅型を中心にし、深型は大物だけに限定します。
衣類は、掛ける収納を多めにして出し入れを簡単にするとよいでしょう。浅い収納は在庫の重複買いと行方不明を防ぎ、結果として物の総量も自然に減っていきます。
玄関→洗面→ミニクローゼット|一直線にして床置きを阻止
帰宅してからLDKに入るまでの数十秒が、散らかり始める分岐点です。玄関で荷物を降ろし、すぐ手を洗い、アウターとバッグをしまってからリビングへ。ここを一直線に設計すると、床置き・椅子置きが激減します。
鍵や書類、通園通学セットの居場所もこの動線上にまとめておくと、翌朝の身支度が驚くほどスムーズになります。
シューズインクロークにコート・傘・バッグ・ベビーカーの定位置
シューズインクローク(SIC)は「靴+外で使う物」の拠点にします。コートはポールとフックを併設し、家族分の定位置を固定しましょう。濡れた傘は受け皿付きの置き場、ベビーカーやアウトドア用品は通路をふさがない壁面寄せにおきます。
バッグは床置きになりがちなので、肩掛けのまま掛けられる高さのフックを用意し、子ども用は低めの位置に重ねて設置します。土間側に浅い棚を一段つくり、マスクや消毒、宅配ハンコなどをまとめると動作が一気に短縮します。
玄関→手洗い→ミニCL→LDKの直線動線
玄関ホールから最短で手洗いにアクセスできる配置が理想です。手洗い後は、ホール脇のミニクローゼット(ミニCL)でアウターとバッグを収納し、そのままLDKへ向かえるようにします。
動線が折れ曲がるほど荷物の仮置きが発生するので、壁の凹みに手洗い+収納をまとめるなど、通過中に完了するレイアウトを意識します。ミニCLは「掛ける収納」を主役にし、引き出しは最小限にすると、出しっぱなしを防げます。
郵便物・鍵・通学セットの置き場所
玄関からLDKに入る前に、一時置きと仕分けができる置き場所を設けます。鍵はトレー固定+壁フックの二段構え、郵便物は「要確認」「保管」「破棄」の三つに自動的に分かれる仕組みを用意すると良いでしょう。
連絡帳やプリントはダイニング脇に溜まりがちなので、動線上のニッチや浅い棚で受け止め、夜までに空にするルールにしてみましょう。通園・通学セットは翌朝そのまま持ち出せる位置に吊るしておくと、翌朝のバタつきがなくなります。
LDKが散らからないレイアウトと小さな収納

LDKで散らかるのは、物のゴールが遠いからです。テーブル上に再び集まる紙類や充電中の端末は、ダイニング脇に浅い受け皿を用意すれば自然と戻ります。
テーブル上を空にするダイニング脇ニッチ
ダイニング脇に幅60〜90cm、奥行き10〜15cm程度のニッチを設け、置く物は〈書類〉〈筆記具・小物〉〈端末と充電〉の3ジャンルだけに絞ります。A4が縦で収まる仕切りと、2〜4口のコンセント(できればUSB付)を用意します。できれば扉付きにして視界をすっきり保つのがおすすめです。
細々ものは浅い可動棚+ラベリングで定位置化
リモコン、電池、薬、文具、テープ、体温計などの細々したものは、奥行き20〜30cmの可動棚に浅いトレーを並べ、用途別にラベリングします。家族別ボックスを一つずつ用意すると、散らかりやすい個人アイテムの行き先がわかりやすいです。
テレビボードは観音開きではなく浅い引き出し中心にして、ゲームソフトは背表紙が見える向きで前列のみ収納すると迷子になりにくいです。
キッチン&パントリー|買う→しまう→調理→片付けを一直線に
キッチンは散らかりの発生源No.1。解決策はシンプルで、「買い物袋を置く→冷蔵・常温に仕分け→調理→配膳→片付け」までを一直線に並べること。買ってきた物の「仮住所」を先に決め、在庫が見える浅い棚でダブり買いを防ぎます。
背面は引き出し、パントリーは「浅め×分類」がカギ
観音開きの棚は「見えない奥」を生みやすいので、背面収納は引き出し中心にします。
- 上段はカトラリーと毎日使う調理ツール
- 中段はボウル・ザル・保存容器
- 下段は鍋・フライパンなど重い物
パントリーは奥行き20〜30cmの浅い可動棚を基準にし、カテゴリごとにバスケットで区切ります(乾物/缶詰/粉もの/お菓子/非常食など)。前面1列置きを徹底し、購入日・開封日を小さくメモしましょう。来客用や季節物は最上段、回転率の高い物は目線~腰の高さに集約すると、取り出しと戻す動作が最短になります。
生ゴミ・資源の仮置き動線を先に決める
片付かない原因のトップは、捨て場所が遠いことです。シンク足元はペダル式や引き出し一体型のゴミ置きにして、調理しながらゴミを捨てられるようにします。
資源ごみは「回収日までの仮置き」をキッチン近くで完結させます。勝手口やパントリー奥に45Lの大きなペールを1つ置くより、10〜20L程度の小さめペールを2〜3個(紙/缶・瓶/ペットなど)を作業動線上に並べ、いっぱいになったら袋ごと屋外へ移す方式のほうが、歩数が短くニオイもこもりにくいです。
洗濯動線|ランドリー直結で「洗う→干す→しまう」を一直線に

洗濯が散らかりの温床になるのは、工程が家じゅうに分散しているからです。理想は、洗う→干す(または乾燥)→たたむ→しまう、の4工程を同じフロア、同じエリアで連続させることです。
室内干し・畳む台・タオル収納を同空間に
「干す→たたむ→しまう」を一部屋で完結させます。室内干しは天井物干しや昇降式ポールを常設し、洗濯機の近くに並行配置します。除湿機とサーキュレーター用にコンセントを用意しておくと、雨の日もここだけで回せます。
畳む台は壁付けのカウンター(奥行45〜60cm)を一枚。高さはキッチンと同等にして、下に浅い引き出しを設け、ネット・ハンガー・ピンチなどすぐ使う道具をまとめます。取り出し→戻すが一手で済むので、山ができません。
タオルは洗面から片手で届く高さに、浅い可動棚を。フェイスタオルは腰高、バスタオルは目線やや下に置くと補充がスムーズです。洗剤や詰め替え類は奥行20〜30cmの棚に一列のみで並べ、“前後二列にしない”をルールに。在庫が見えるだけで、迷いとムダ買いが消え、動きも短くなります。
まとめ
片付く家は、「動線×定位置×浅い収納」という工夫があります。できるだけ、動作を一直線にすること、その動線上に物の置き場があること、そして奥にしまわず、常にものが見える「浅い棚」を使うことが片付くコツです。
すぐにしまえる工夫があれば、出しっぱなしを防げますから、自然と片付く家になります。
無料でお送りいたします