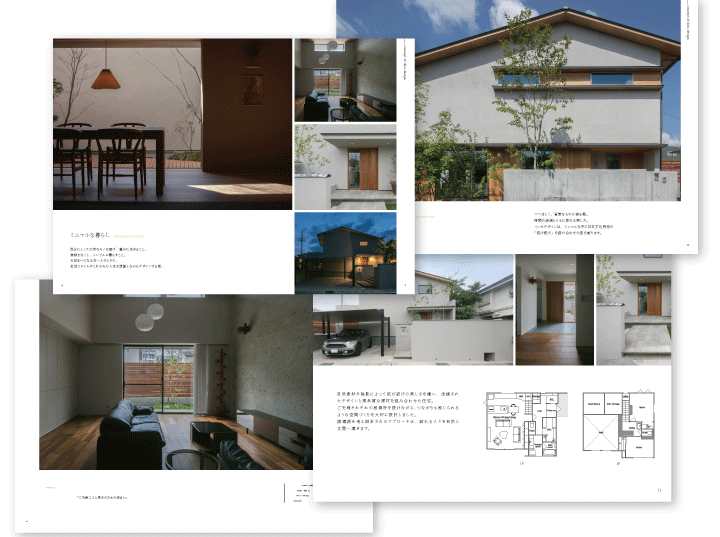注文住宅に必要な保険の種類まとめ!補償内容と保険料もチェック

注文住宅を建てるとき、多くの方が夢や希望を膨らませる一方で、「保険は何に入ればいいの?」と迷ってしまうのも事実です。住宅は人生で最も大きな買い物のひとつ。だからこそ、万が一のリスクに備えて「住宅保険」について知っておくことが大切です。
住宅保険と一口にいっても、補償内容や目的によっていくつかの種類があります。ここでは、主に新築住宅に関わる3つの保険「火災保険」「地震保険」「団体信用生命保険(団信)」を中心に、基礎知識と選び方をご紹介します。
住宅保険とは?基本の考え方

注文住宅を建てたとき、なぜ保険に加入しなければならないのか、基本的な考え方について説明します。
新築時に住宅保険に加入する必要性
新築住宅は新しいからといって、災害や事故から無縁というわけではありません。火事や水害、地震など、さまざまなトラブルが突然やってくる可能性があります。住宅保険は、そうしたリスクによる損害からマイホームを守るための備えです。
とくに、自己資金だけで家を建てる場合は加入が任意となるものもありますが、住宅ローンを利用する場合は、加入が事実上必須とされる保険もあります。以下で詳しく見ていきましょう。
住宅ローンを利用するなら火災保険は必須
住宅ローンを組む際、金融機関から火災保険への加入を求められるのが一般的です。ローンを組んだ住宅が火災で全焼してしまえば、担保となる資産が失われ、貸し倒れリスクが発生するからです。
多くの場合、ローンの契約条件として火災保険に加入する必要があり、保険期間も住宅ローンの返済期間に合わせて10年~30年と長期になることが多いです。
火災保険と地震保険はセットで考える
住宅に関する保険の種類は、大きく分けると火災保険・地震保険がありますが、この2つはセットで加入するものです。
火災保険が補償してくれるのは火災の被害だけじゃない
火災保険は、住宅や家財に対する損害を補償する保険です。しかし、意外と知られていませんが、火災保険の補償は「火事」だけではありません。火災だけでなく、
- 風災(台風・竜巻など)
- 水災(大雨による洪水・土砂災害)
- 雪害
- 落雷
- 爆発
- 外部からの物体の衝突
- 盗難
などの被害も補償対象に含めることができます。
たとえば、近年増えている台風やゲリラ豪雨による浸水被害、突風による屋根破損、隣家の火事によるもらい火なども補償の対象になりえます。
また、給排水設備の故障による水漏れや、空き巣による窓ガラスの破損も、契約によっては補償されます。つまり、火災保険は住宅に対する「総合的なリスク保険」として機能するのです。
補償範囲は契約内容によって異なり、たとえば「建物のみ」「建物+家財」のように選ぶことが可能です。大切な家具や家電が多い家庭では、家財も補償対象に含めておくと安心です。
火災保険の保険料の相場と契約期間
保険料は建物の構造(木造・鉄骨造など)や築年数、地域、補償内容によって異なりますが、新築の木造住宅であれば、5年契約で5万~13万円程度がひとつの目安です。マンションであればさらに安くなる傾向があります。
契約期間については、以前は最長10年の契約が可能でしたが、2022年10月の制度改定により、現在は最長5年までに短縮されています。
これは自然災害の増加により、保険会社が将来のリスクを見通しにくくなったためです。保険料は一括払いが基本ですが、契約更新時に見直しの機会を設けることができます。
地震保険は火災保険の付帯が前提
地震保険は、地震・噴火・津波などによる建物や家財の損害を補償するものですが、火災保険に「付帯」する形でしか契約できません。つまり、地震保険だけ単独で加入することはできないのです。
火災保険では地震による火災は補償されないため、南海トラフ地震や首都直下型地震のリスクが高まっている今、加入しておく意義は大きいでしょう。
地震保険の補償内容と保険料相場
地震保険は、火災保険に付帯する形で加入し、地震・噴火・津波による損害を補償します。補償金額は「地震保険に関する法律」という法律で定められており、火災保険の補償額の30〜50%が上限です(例:火災保険で建物2,000万円の補償がある場合、地震保険では最大1,000万円まで)。
このため、大規模な地震で建物が全壊しても、地震保険だけでは再建費用をまかなえない可能性があります。そこで、保険会社によっては「地震上乗せ補償特約」などの独自商品を用意しており、火災保険の補償額に近い金額まで補償を上乗せできるケースもあります。建て替え費用までしっかり備えたい方は、こうした特約の有無もチェックしておくと安心です。
地震保険の保険料は、建物の構造や所在地によって大きく異なります。たとえば、東京都の木造住宅(建物2,000万円・家財1,000万円)で5年間契約した場合、保険料は合計で約10万円前後が目安です。なお、耐震等級が高い建物や免震構造の住宅では、割引制度が適用されることもあります。
住宅ローンを組むときには団体信用生命保険に加入

直接、住宅に関する保険ではないのですが、ローンを組むときは、団体信用生命保険に加入するのが一般的です。
団信の種類(がん団信・三大疾病団信など)
団体信用生命保険、通称「団信(だんしん)」は、住宅ローンの契約者が死亡または高度障害状態になった場合に、残りの住宅ローンを肩代わりしてくれる生命保険です。ほとんどの金融機関では、この団信への加入が融資の条件となっています。
最近では、標準の死亡保障だけでなく、
- がん団信
- 三大疾病団信
- 就業不能団信
など、より幅広いリスクに対応したプランが用意されています。保険の内容によって、住宅ローンの金利に0.1〜0.3%程度上乗せされるのが一般的です。
団信の保険料(実質的な支払い)と負担感
団信の保険料は、通常は「住宅ローン金利に上乗せ」される形で支払います。つまり、月々の返済額の中にすでに保険料が組み込まれているため、別途支払いが発生するわけではありません。
ただし、より手厚い保障を選ぶと金利が上がるため、結果的に総返済額が増える点には注意が必要です。将来の健康リスクと家計のバランスを見ながら、無理のないプランを選ぶことが大切です。
注文住宅に必要な保険の種類、どう選ぶ?

おおまかに住宅保険の種類はお分かりいただけたと思います。では具体的に、どのような保険を選べば良いのか、選び方についてまとめました。
ライフスタイルとリスクに応じて検討する
保険選びで大切なのは、「どんなリスクに備えたいのか」を明確にすることです。たとえば、洪水リスクのある地域であれば水災補償を含む火災保険が欠かせませんし、小さなお子さんがいる家庭なら家財の補償もしっかり検討した方が良いでしょう。
また、将来的な転居や二世帯化など、ライフスタイルの変化も視野に入れて契約内容を考えると、後悔のない選択ができます。
補償内容と保険料のバランスがカギ
「全部に備えよう」とすると保険料が高額になってしまうため、必要な補償と、なくても良い補償を仕分けることが大切です。各保険会社の見積もりを比較し、特約の内容や免責金額(自己負担額)にも注目しましょう。
比較サイトや無料相談サービスを活用するなどして、お財布にやさしく、なおかつ、ほしい補償がついている保険を探します。とくに新築時は手続きが多いため、迷ったら、ファイナンシャルプランナーなどプロのサポートを受けながら進めるとスムーズです。
まとめ
注文住宅を建てる際には、火災保険、地震保険、団体信用生命保険(団信)という3つの保険を中心に検討することが欠かせません。
火災保険と地震保険は住宅そのものを守る備えであり、団信は住宅ローン返済を家族に残さないための重要な保険です。どの保険にもそれぞれの役割がありますが、補償内容や保険料には違いがあるため、しっかりと比較検討し、自分に合ったプランを選ぶことが大切です。
安心して暮らすために、保険は家づくりの見えないけれど大切な土台となるもの。ぜひ納得のいく形で準備を進めていきましょう。
無料でお送りいたします