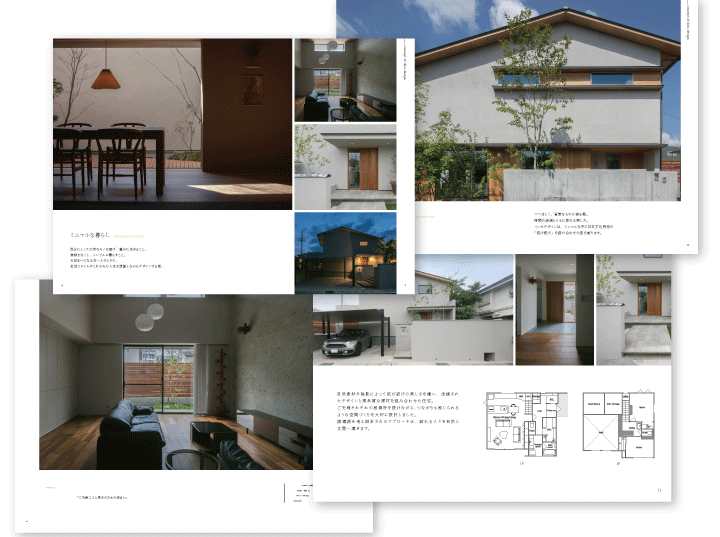住宅ローン控除はいつまで? 2025年までの変更点とメリットを解説

住宅を購入するときにぜひ検討したいのが「住宅ローン控除」です。
住宅ローンを利用して家を購入する際、一定の条件を満たすことで、所得税や住民税から税額控除を受けることができるこの制度。しかし、「住宅ローン控除は2021年で終了した」と思っている方も多いかもしれません。
実際には、2022年の税制改正によって2025年まで延長されています。これにより、多くの方が引き続きこの制度を利用することが可能な状況です。
この記事では、住宅ローン控除の概要や利用できる期間、そして今後予定されている制度改正について詳しく解説します。現在、住宅ローン控除の適用を受けている方、これから住宅ローンを利用して住宅購入を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した場合に一定の要件を満たせば年末の借入残高に応じて計算された額を所得税額や住民税額から控除できる制度です。
この控除は、当初控除期間が10年間、控除額は年末時点の借入残高の1%でした。その後、2021年の入居から控除期間が13年間に延び、さらに2022年1月1日以降の入居からは控除額が借入残高の0.7%となりました。こう考えると次々と条件や要件が状況に応じて変わっていることがわかります。
住宅ローン控除期間については、コロナ禍の経済影響を考え、10年から13年になりました。控除率が1%から0.7%に下がったのは、近年の低金利下で住宅ローンの金利が1%を下回るケースが多くみられたことで、利息額と控除額のバランスを考えた結果です。
住宅ローン控除は、正確には、住宅借入金等特別控除といいます。この制度は、新築・中古住宅、リフォームなど幅広く適用され、高所得層にとっても特に大きな節税効果が期待できます。ただし控除を受けるためには、住宅面積・自己使用・借入金の金額といった一定の条件を満たす必要があります。特に、注文住宅を検討している方は、設計や建築基準に注意が必要です。
2022年以降の変更点

2022年から適用されている控除額の上限や減税期間の変更、そしてそれに伴う条件についてまとめてみましょう。
特に、住宅のエコ性能に応じた控除率や、新エネルギー基準の導入といった環境問題に関連するものが影響しますので、エコ住宅を検討する際は重要な要素になります。
2022年税制改正では、控除率の変更、控除年数の変更、借入限度額の変更、所得要件の変更がおこなわれました。控除率は、ローンの年末残高の1%から0.7%に引き下げられました。控除年数は、新築住宅の取得に限り13年に変更されました。中古住宅や住宅の増改築は10年のままですし、2024年以降に入居する場合も控除年数は10年ですので注意が必要です。借入限度額は、3,000万円に変更されました。中古住宅の取得や住宅の増改築は2,000万円です。
2024年・2025年入居の新築住宅取得については2023年までに新築の建築確認を受けている場合は、借入限度額が2,000万円となります。所得要件は、2022年以降2,000万円以下に引き下げられました。
気にしたい認定長期優良住宅に係る控除
建築購入を検討している方にとって重要な住宅性能によって変わる控除について説明します。いわゆる「認定長期優良住宅」に関する住宅ローン控除です。一般の住宅とは改正内容が異なります。
住宅ローン控除の対象となる住宅の種類は、一般の住宅以外に、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の4つに大別されています。
認定住宅は、長期にわたって良好に使用するための構造や設備を有する住宅として一定の基準を満たして認定を受けた「認定長期優良住宅」と、二酸化炭素の排出基準など一定の基準を満たした「認定低酸素住宅」の2つにさらに分かれています。
ZEH水準省エネ住宅は、エネルギー環境に配慮して、断熱・省エネ・創エネを組み合わせて1次エネルギー消費量の収支ゼロを目指して設計された住宅です。
省エネ基準適合住宅は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき省エネルギーの一定基準を満たしている住宅です。
認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅は、控除率と所得要件は変わりませんが、控除年数が13年、借入限度額は一般の住宅よりも高く設定されています。
高所得層にとっての住宅ローン控除のメリット

高所得層にとって住宅ローン控除は、これまであまり大きなメリットがなかったとされることがあります。その理由として挙げられるのが、控除額の上限です。住宅ローン控除には控除額の上限が設定されていますが、高所得層が多額の住宅ローンを組んでも控除で得られる減税額が限定的でした。特に、高額物件を購入した場合であっても、控除対象となる借入残高の上限の壁で大きなメリットが得られませんでした。
また、住宅ローン控除は所得税から差し引かれるため、高所得者でも所得税の額を超える部分は控除されません。そのため、そもそも所得税の一部しか控除の恩恵を受けられない場合があるのです。さらに、年収制限も大きく影響します。これまでの年収3,000万円の制限は、高所得層に分類される人たちの控除適用外となる可能性を上げていました。高所得層は自己資金を多く持っているため、ローンを利用しなかったりローンの金額が少なかったりと、住宅ローン控除を受けずにいる場合もあります。
しかし、近年では、控除制度が変わり、一部の高所得層向けに優遇措置が見直される場合が出てきました。全体としては低・中所得者層により多くのメリットがある制度とされてきましたが、高所得者であっても十分にメリットを受けられます。
年収が高いほど所得税率が高くなりますので、住宅ローン控除を受けることができれば控除額が大きいので、節税効果も高いということになります。特に30代から50代の高所得層は、住宅ローン控除を活用することで、最大で数百万円の税金を抑えることも可能です。
また、エコ住宅に関する控除は近年の税制改革で大きく変更されているポイントのひとつです。断熱性や太陽光発電システムなど、長期的に環境と経済に優しい選択肢を検討することで、住宅ローン控除の恩恵を最大限に活用できます。
さらに、注文住宅を検討している場合は、住宅ローン控除は大きなメリットになります。ローン控除によって返済計画も緩やかに進めることができますし、エコ住宅などを検討することで、より有益で長期的な資産形成にもつなげることができます。
住宅ローン控除の適用を受けるには?
住宅ローン控除の摘要を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 購入する住宅が、自分が居住する住宅であること
購入する住宅の床面積が50平方メートル以上、かつそのうちの2分の1以上が居住用である必要があります。 - 住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 借入れている住宅ローンが、10年以上の借入期間であること
対象となる住宅ローンが10年以上にわたって返済するものでなければならないため、特に繰上返済時は注意が必要です。繰上返済後に当初の契約により定められていた最初に返済した月から、短くなった償還期間の最終の返済月までの期間が10年未満になれば、住宅ローン控除は受けられません。そのため、住宅ローン控除適用期間中に繰上返済を行う際には、事前にシミュレーションをして、返済後の借入期間を確認することをおすすめします。 - 住宅の引き渡しおよび工事の完了から6ヵ月以内に入居していること
購入した住宅に6ヶ月以内に入居し、年末まで居住していることが必須条件になっています。入居が遅れたり、別の住まいに移ってしまったりすると、控除が適用されません。 - 現行の耐震基準を満たしていること
基本的には、これらの条件のすべてを満たすことで住宅ローン控除の適用を受けることができますが、具体的な状況によっては例外や特例が適用される場合もあります。たとえば、改築の場合の床面積要件は、全体の床面積ではなく増改築した部分が一定以上の要件を満たせば控除対象になることがありますし、特定の災害被災者や低所得者向けの支援制度によって、通常の年収要件を超えていても適用できる場合があります。これらの特例は申告年度によってことなってきますので、一部の条件を満たさない場合でも、自分が該当する特例があるか、別の控除制度で特例扱いにならないか、といった確認をすることが重要です。確定申告を提出する前に、税務署や税理士に相談すると細かな状況に応じた対応の仕方などをアドバイスしてくれます。
2025年までに住宅購入を考えるべき?

これまでの経過を考えると、2025年以降に住宅ローン控除がどのように変わるかは不透明ではありますが、制度の変更や終了は十分に考えられます。そうなると控除があるうちに住宅を購入してローン控除を利用することで、長期的な税負担を軽減し、賢く資産を形成することを検討することが重要になります。
住宅購入を検討するうえで、省エネルギー住宅や長期優良住宅は大きなポイントとなります。現行の住宅ローン控除を大きな節税が見込めますし、今後のエネルギー問題は社会全体の課題としてさまざまな対策が打たれていくことが期待されているからです。さらに、13年間の控除適用は長期的な税負担の低減になります。
住宅ローン控除が2025年に終了、またはさらに条件が厳しくなる可能性がゼロでない以上早めの行動が必要です。特に注文住宅の場合は、設計や施工に時間がかかります。控除を受けるためには、しっかりとスケジュールをたて、早めに準備を進めることで税制の期限を見据えた計画をたてることができます。
エコ住宅で住宅ローン控除を最大限に
住宅ローン控除においてはが、認定長期優良住宅が優遇されていることは前述していますが、その中でも、エコ性能の高い住宅は今後住宅購入を検討するうえで外せない条件になっています。省エネルギー性能が高い住宅に対しては2022年以降の税制改正により、より高い借入金上限が設定されていますし、今後もこのような処置は続くことが期待されているためです。エコ住宅を選ぶことで、より大きな節税効果を受けられる可能性が高いのです。
エコ住宅は、通常の住宅に比べて借入金の控除上限が高く設定されています。例えば、省エネ基準適合住宅の借入金控除の上限は4,500万円です。
もちろん、節税対策だけではなく、長期的に考えてもエネルギー効率が高い設備を導入することで、日常の光熱費が削減され、コスト削減に役立ちます。
ではどのようにしてエコ住宅を選べばいいのでしょうか。注文住宅を検討する際に、エコ住宅としての性能を確認することは最も重要なポイントのひとつです。
まずは断熱性能です。壁や窓の断熱性が高いほど、外気の影響を受けにくく、冷暖房費が節約できます。次にエネルギーに関することとして、太陽光発電システムや高効率給湯設備などがあげられます。自家発電が可能な住宅は、光熱費を削減するだけでなく余剰電力を売電できますし、エネルギー効率の高い給湯器は日常の使用エネルギーを削減できます。
こういったエコ住宅の要素を取り入れることは、住宅ローン控除を最大限に活用できるだけでなく、自分たちの生活環境にも大きなメリットを与えます。
まとめ

住宅ローン控除の内容は、毎年の税制改正で少しずつ変わっています。現状では省エネルギー住宅や長期優良住宅に該当すれば控除期間が延びたり、条件が緩和されていたりしています。しかし、今後の見直しによっては優遇されていた条件が撤廃される可能性もあるのです。さらに、子育て支援など政策によって実施された優遇処置は簡単に変更されます。
今後の市場の動向や景気の動き、政策によってはさらに内容が変わる可能性もあります。常に動向をウォッチして、制度改正の動きがあれば、早めに対処できるようにしておくことが大切です。
2025年までの住宅ローン控除を上手に活用することは、高所得者層にとっては大きな節税メリットとなります。特に、省エネルギー住宅や長期優良住宅など、注文住宅での購入を検討している場合は、今後の税制改正をしっかりと理解し、計画的に購入を進めることをおすすめします。
無料でお送りいたします